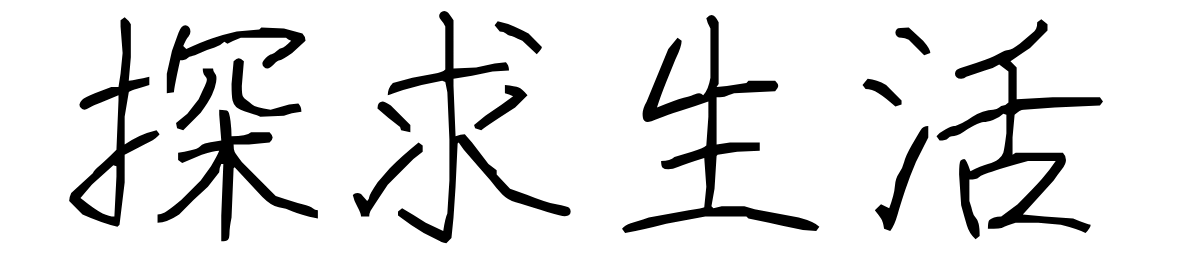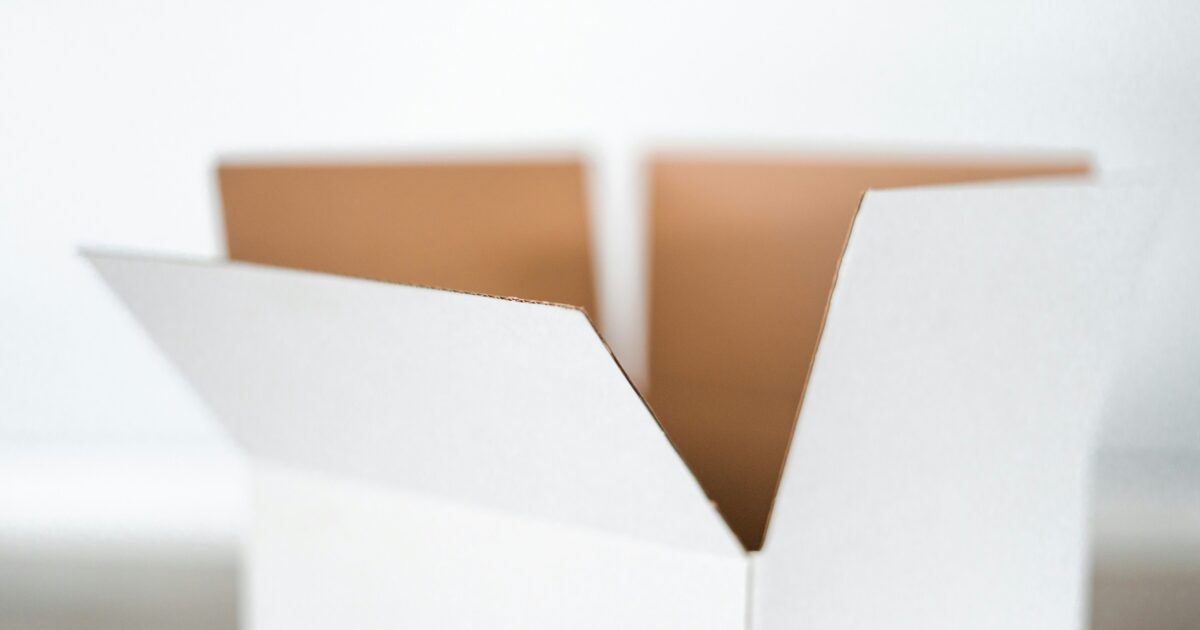買いすぎてどうしようかという服は、使ってくれる人、必要としている人に譲るという方法があります。
方法を、5つまとめました。
いっしょに、手放すときの注意点も確認しておくと安心です。
どうしようもなく地域の古着回収などで処分することもありますが、だれかの役に立つような手放し方を知っておくと、買いすぎた後悔を前向きにするような選択もできるのではないでしょうか。
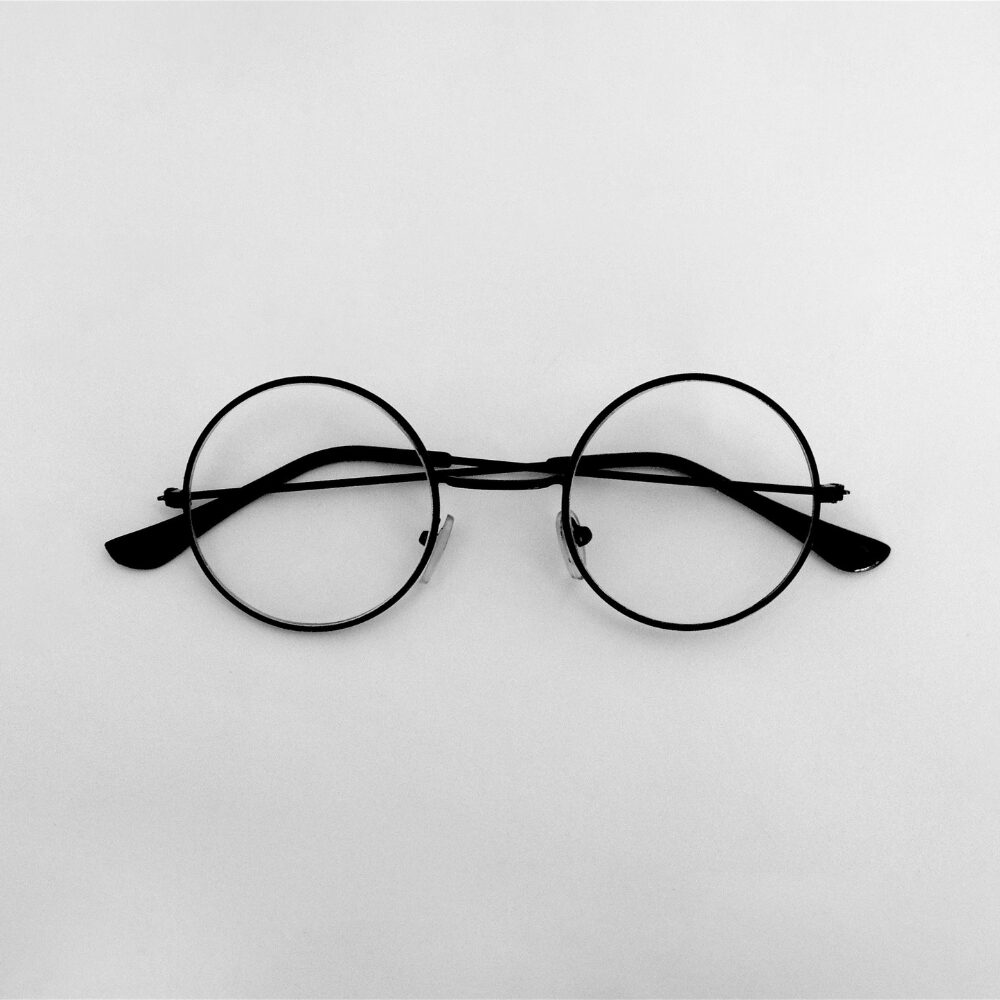
この記事を読むと、買いすぎた服の手放し方と、そのときの注意点を確認することができます。
目次
みんなの被服費の平均は?
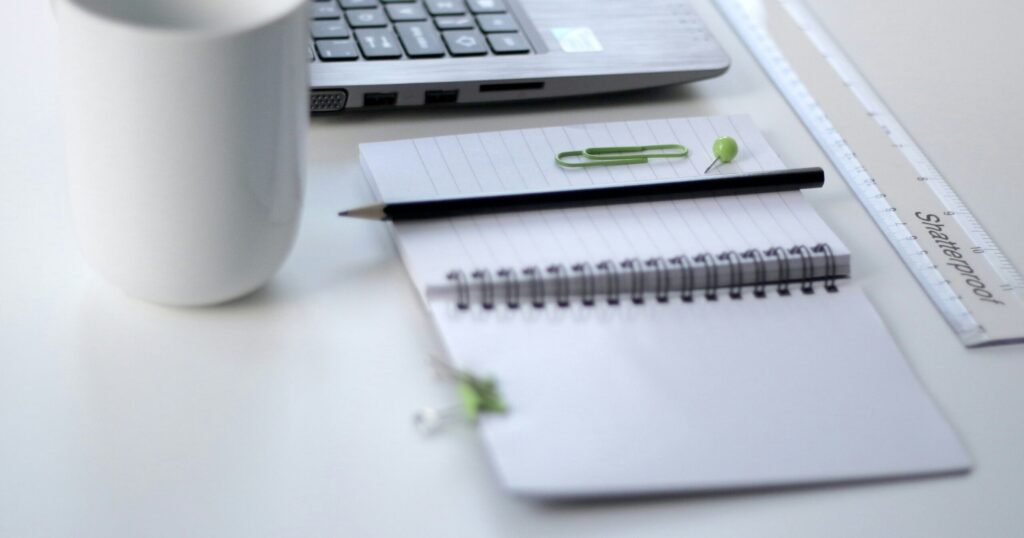
2人以上の世帯では、被服費の平均は毎月9,985円という数字が出ています。
これは、2024年の家計調査(総務省統計局家計調査)の結果です。
2年ぶりに増えたことも、明らかになっています。
単に服を多く買うようになったからなのか、あるいは物価が上がったことによるものなのかについては、実質増減率が1.1%と記されているため、前者といえるでしょう。
一般的にはどうなのかを知ることは、自分の現状を客観的に見るきっかけになります。
家計簿も役に立つ
自分は服を買いすぎているのだろうかという判断は、国の平均値と比べるほかに、家計簿をつけることでもできます。
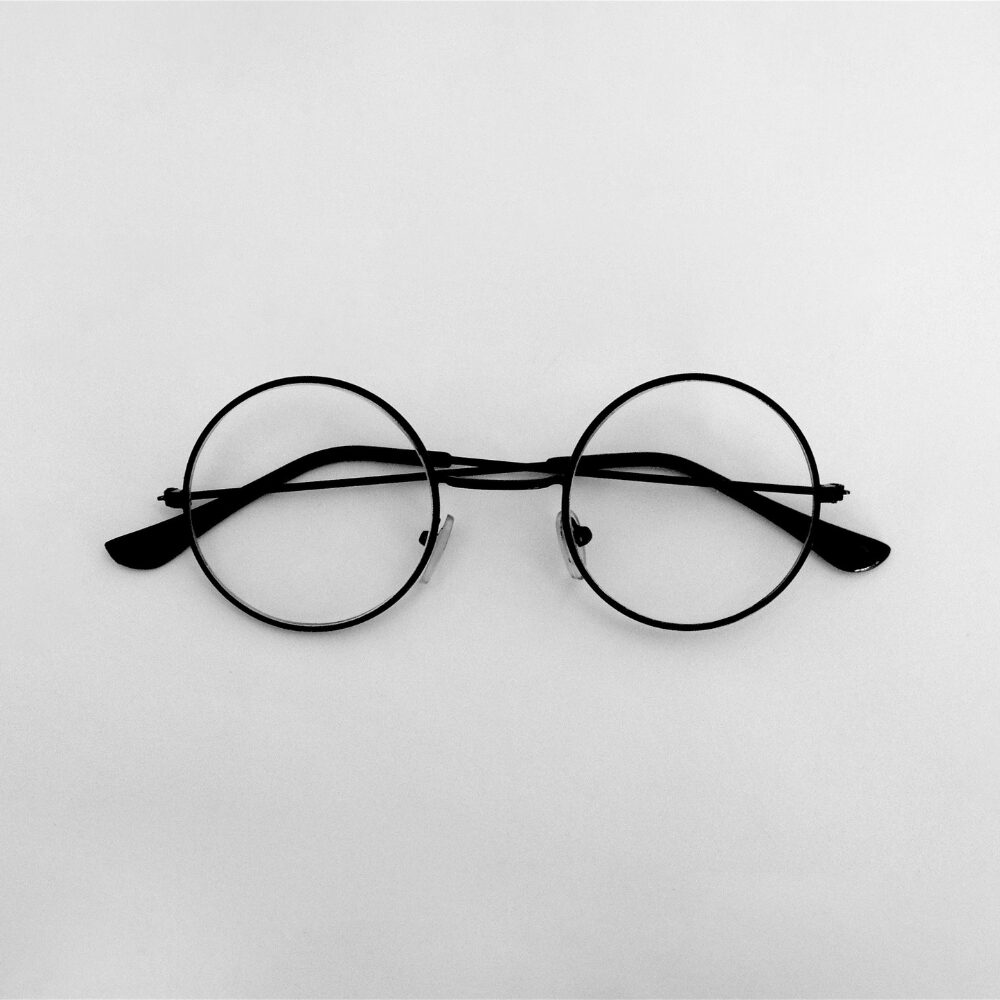
家計のなかで、被服費の占める割合を見てみましょう。
きっと、生活するために必要な被服費もあれば、自分の楽しみのために使われている被服費もあるはずです。もし、家計を圧迫しているようなことがあれば、家計の支出のなにかを見直す必要があります。
つまり、被服費を見直すのか、服は好きに買いたいから他の支出に手を加えるのかということ。
おおざっぱにでも家計簿をつけるようにすると、自分の収入に対して、はたして服を買いすぎているのかということを生活のさまざまな支出と結びつけながら考えることができます。
いったいどのくらいの予算がちょうどいいのかも、決めやすくなるでしょう。
あわせて読みたい記事
▶「家計の見直しは、まずなにからすればいいの?」とお考えのかたには、こちらの記事もおすすめです。
おおざっぱな家計簿といえば、金融庁の家計管理シミュレーターがあります。
これは、家計のおおまかな収支を知るのに役立ちます。
おおよその数字を選ぶだけなので、とても簡単です。
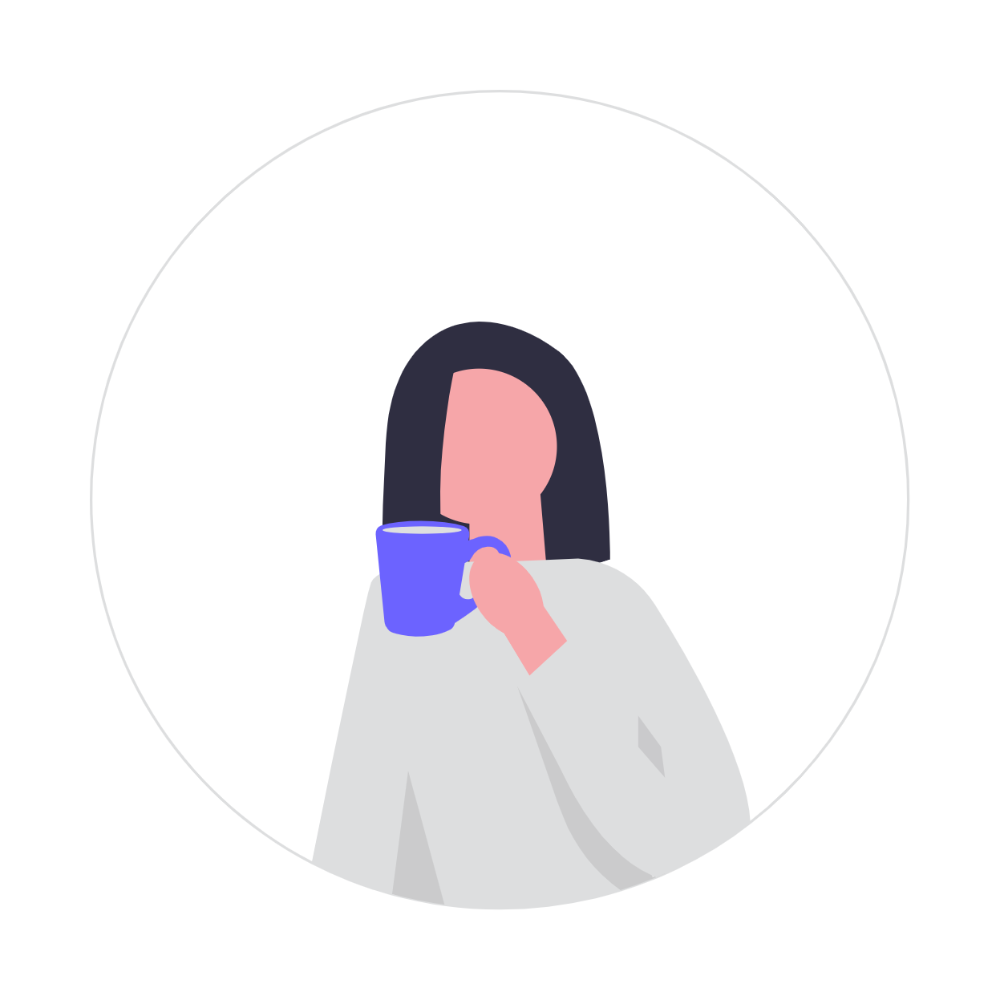
わたしは、すでに家計簿をつけているのだけど……
家計簿をすでにつけているかたで、被服費をかけすぎていると悩むときには、家計の黄金比に当てはめて見直してみるのはいかがでしょう。
エリザベス・ウォーレン氏が著書で提唱した「50(NEEDS):30(WANTS):20(SAVINGS)」は、世界的に有名な家計の黄金比率です。
エリザベス・ウォーレンの家計の黄金比率とは
- エリザベス・ウォーレン氏はアメリカの上院議員で、もとは、破産を専門とする法学教授だった。
- NEEDSは「必要なもの」、WANTSは「欲しいもの」を、SAVINGSは「貯蓄・投資」を意味する。
- 「必要なもの」とは、生活必需品(食費、公共料金、家賃、車のローンや維持費などの固定費)のことであり、また「欲しいもの」とは、贅沢費(外食費、レジャー費用、趣味に使うお金)のこと。
家計再生コンサルタントである横山光昭氏の、家計の黄金比も有名です。
毎月の支出のうち、消費は70%、浪費は5%、投資は25%という支出比率を目指して、90日間、自分のお金の使い方を見直してみましょう。
「横山光昭氏インタビュー記事」より
もしかしたら、服を買いすぎる直接の原因の分析と解消をするのがいい場合もあるでしょう。
買いすぎた服の手放し方

買いすぎてしまった服を手放す方法を、5つご紹介します。
それぞれの特徴を知り、いいなと思うものをお役立てください。
1. 買取業者
買取業者とは、不用品や中古品を買い取り、再販している事業者のことです。
リサイクルショップ、ブランド品買取店、出張買取サービス、オンライン買取サービスなどがあります。
良いところは、専門業者に依頼するだけで手放すことができることです。
難点は、買取価格にあまり期待できないこと、品物の状態によっては買い取ってもらえず、結局ほかの方法で処分しなくてはいけなくなることです。
2. 自分で売り払う
自分で売り払うとは、自分で出品をして購入希望者と取り引きする方法のことです。
メルカリ、ラクマ、ヤフーオークションなどがあります。
最近では、写真を撮るだけで販売商品の概要を作成してくれる機能がついたりと、出品する手間がずいぶんとかからなくなりました。
子ども服は、多少古くても譲ってほしいという人が案外多く見受けられます。
買取業者では買い取ってもらえないことも多い子ども服ですが、そのような物でも必要とされ、重宝されるでしょう。
販売価格を決められるのが、良いところです。
ただし、購入者とのトラブル対応には気をつけなければなりません。
取り引きが無事終わるまで気が休まらないこと、売れるまでは手元に残ったままなのですぐには手放せないことが難点といえます。
3. 友人、知人にゆずる
友人や知人にゆずり受けてもらう方法もあります。
きょうだいが多かったり、子ども服の消耗が早いご家庭には喜んでいただけるでしょう。
また、好みのブランドや着こなし方を知っている相手に、それらと合うものをゆずる場合も喜んでいただけるのではないでしょうか。
大切なのは、引き取ってもらったあと相手が服をどうしたかということにはいっさい関与しないという心づかい、または心構えです。
受け取ってくれた側の負担にならないような気づかいが、欠かせません。
「おさがり」のエピソード
息子が生後8か月の時、おさがりのブルゾンをいただいたことがありました。
とてもかわいらしいデザインのブルゾンで、息子は気に入ってよく着ていました。
息子が着られなくなると、おさがりを待っていた娘も、たくさん着ました。
そんなある日のこと、譲ってくださった方から「サイズアウトしたら〇〇ちゃんに回してあげて」と言われたのです。
万が一、リサイクルショップにでも持ち込んでしまっていたらどうなっていたのかと考えると、ありがたかったおさがりが急に重荷に思えたのでした。
この経験をしてからというもの、自分がおさがりをするときは、受け取っていただいたことの感謝とあわせて「あとはどうしても構わないからね」と一言添えるようにしています。
4. 施設に寄付する
地域の子育て支援センター、児童養護施設、孤児院などで、子ども服の回収をしていることがあります。
私の家の近くにある子育て支援センターには、子ども服の寄付コーナーがあります。
そして、親は必要なものを好きに選んで持ち帰れるようになっています。
買いすぎて持て余している服を、このようにして活かせる場所が身近にもあるのです。
気になる施設があるときは、まずHPや電話で問い合わせるなどして、必要とされているものや寄付の方法を確認することをお忘れなく。
また、自治体によっては、大人用と子ども用どちらの服でも回収できるBOXが設置されていることもあります。(福岡市の衣類回収の例)
この場合は、リサイクルになります。
5. NPO法人に提供する
売ったり、ゆずったり、身近なところに寄付できる施設がないときには、NPO法人に寄付するという方法もあります。
寄付されたものの多くは、発展途上国(以下:途上国)におくられます。
団体によって、寄付されたものを途上国でどのように活かすのかは違いがあるようです。
途上国の販売店などに寄付し、雇用を作るという支援方法や、途上国の古着販売業者に卸し、収入をその国の教育支援資金にして活動する方法、国内で再販し、その売り上げを途上国などの支援活動にあてる方法などです。
国内の被災地や、貧困家庭に寄付する活動を行っている団体もあります。
寄付をするNPO法人がどのような取り組みをしているのかを知ると、買いすぎた服にも意義を持たせるような手放し方ができるのではないでしょうか。
手放すときの注意点

手放すときに気をつけることは、3つあります。
状態
ここまでにまとめてきた手放し方には、買い取り、自分での販売、ゆずる、寄付するとありましたが、受け入れられる衣類の状態はそれぞれ違います。
まず、自分で売るときには、買い手に服の状態がよく分かるよう工夫を凝らす必要があるでしょう。
これは、トラブル防止のためにも大切です。
そして、買い取り、ゆずる、寄付するときには、それぞれに決められている基準の確認をしてからがいいでしょう。
個人情報
名前が刺繍されていたり、書かれているときは、消したり、取りのぞいたりして個人情報がむやみに漏れないようにしましょう。
法律・条例
地域の回収、古着処分に関しては、法律や条例があります。
多くは資源ごみとして回収されますが、回収方法は自治体によって違うことも。
回収BOXが設置されている自治体もあれば、リサイクルデーを設けて回収しているところもあります。
お住まいの地域のHPなどを確認してからがいいでしょう。
さいごに
ときには、服を買いすぎて後悔したり、落ち込んだりすることもあります。
けれども、使ってくれる人や必要としている人に役立ててもらえると、沈んだ気持ちもすこしは立ち直れるような気はしないでしょうか。
社会の循環のなかに服を手放しながら、「買うこと」で満たそうとしていた気持ちを見直すことができると、これまでの自分とはなにかが変わるように思うのです。
「いつも服を買いすぎる」ということを解決したいかたには、こちらの記事もおすすめです。
▼ あわせて読みたい記事


最後までお読みいただき、ありがとうございます。