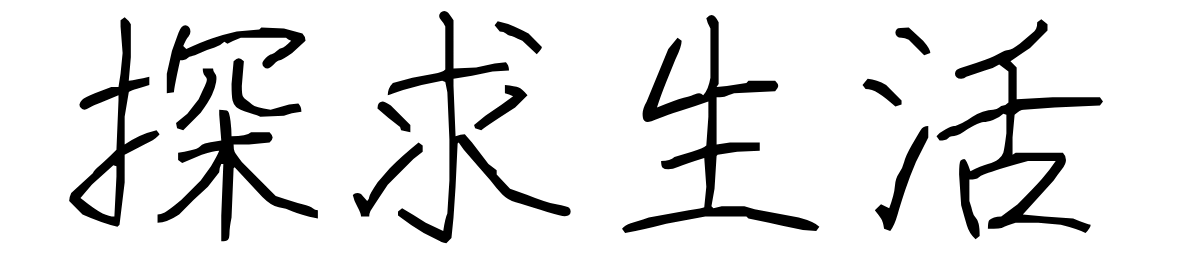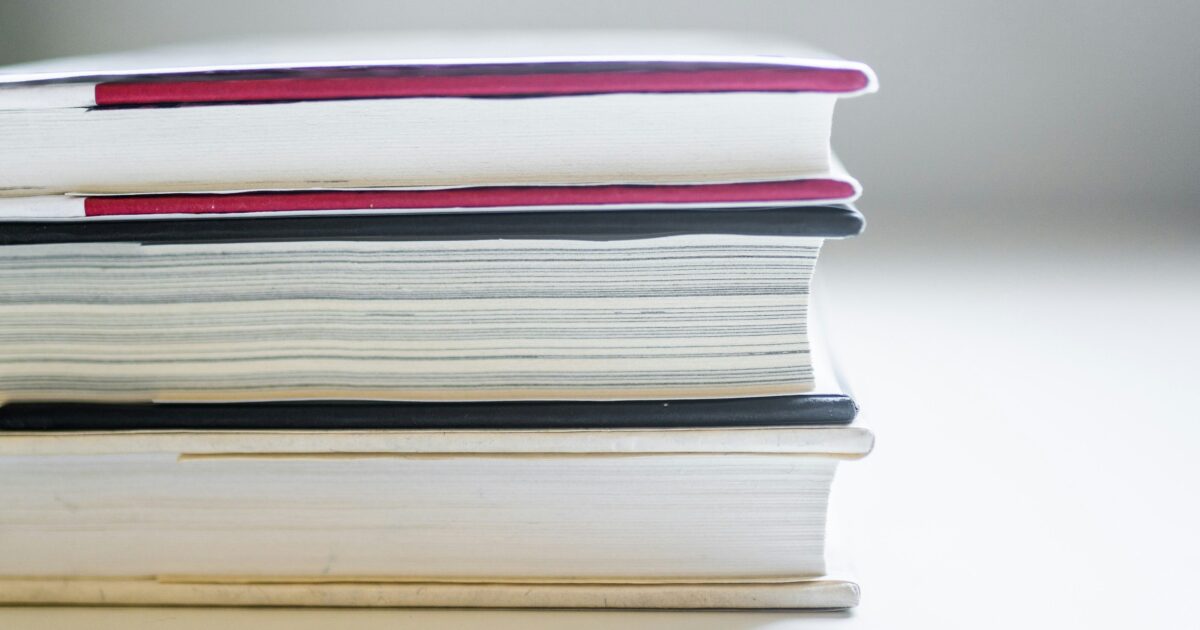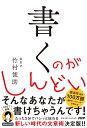なにも経験がないところからライターを目指すとき、「書籍から学ぶ」という方法があります。
ライターは、文章を書くことを仕事とします。
それゆえ、文章を読むことで学べることは、さまざまあるのです。
どのようなことを学びたいと思ったから読んだのか、また、実際に内容はどうだったのかを、6冊分まとめてみました。
ライターを目指すうえで読んでみようかと悩んでいる本があるとき、なにを読んだらいいのかわからないときのご参考までに——。
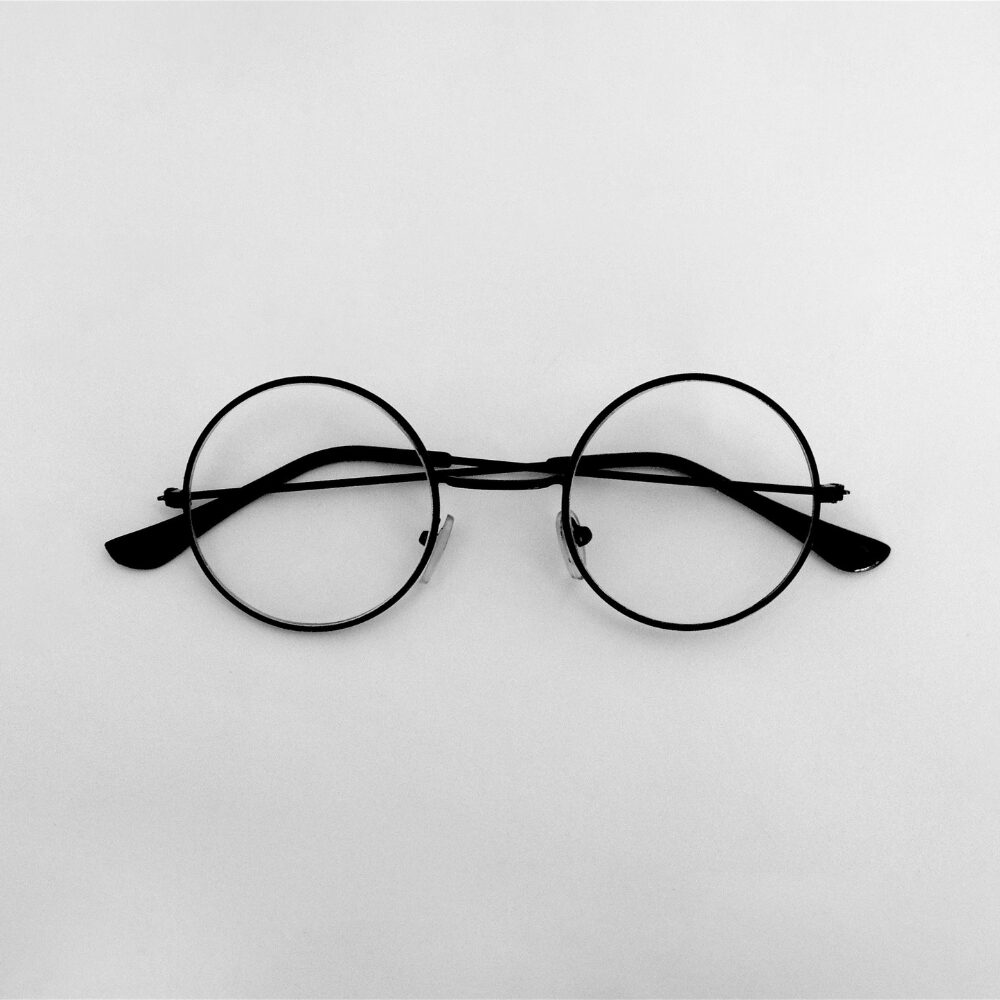
この記事を読むと、「ライターになるために読むといい本」についての、意図・目的に対して実際にはどのような内容だったのかを知ることができます。
自分に必要な本を選ぶときの、参考になるでしょう。
1. 20歳の自分に受けさせたい文章講座
この本を読むことにしたのは、頭のなかにあることを文章にするための方法を学びたいと思ったからです。
さまざま考えてはいるけれど、言葉と文字にして伝えることがあまり得意ではありませんでした。
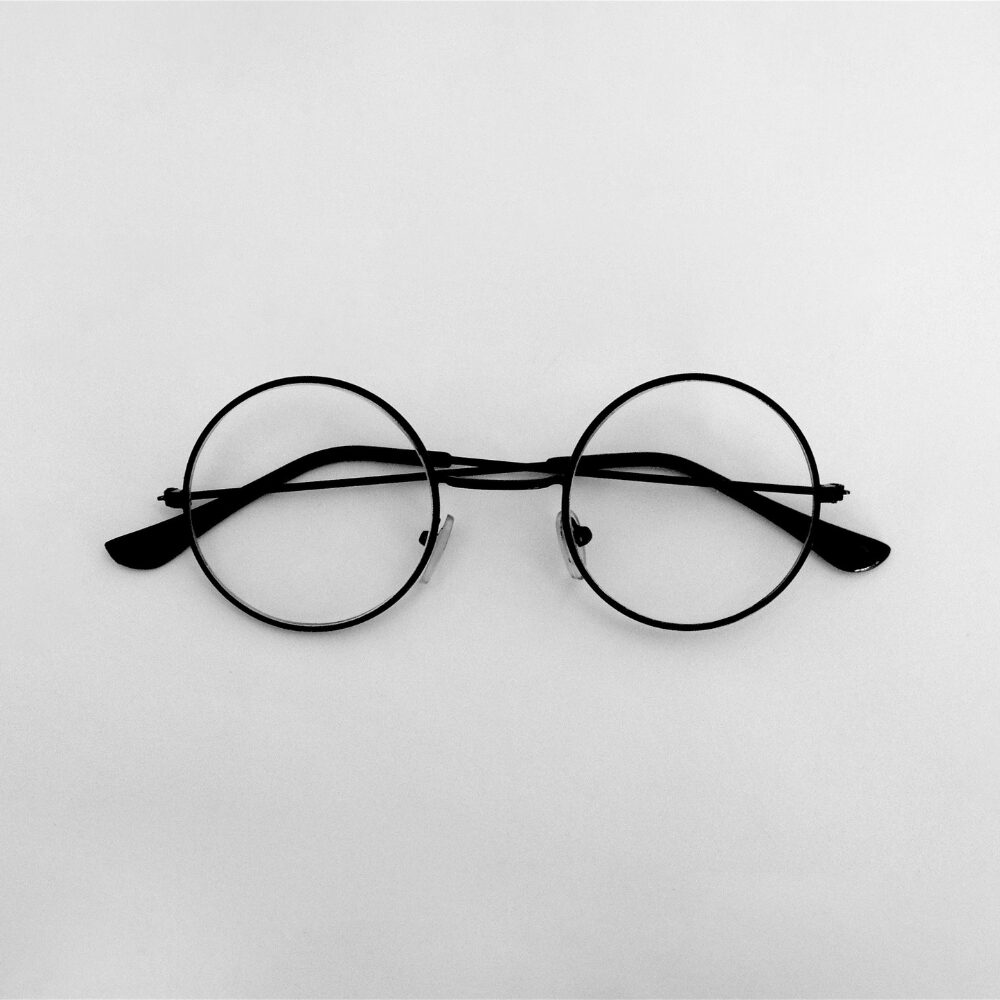
内容は、期待どおりでした。
まず、「話せるのに書けない」という問題を解決するための方法が、詳しく記されています。
そして、読み手に伝わる文章を書くための考え方と方法についても、順を追ってまとめられています。
そのなかで、いまでもとくに役立っているのは「自分の頭のなかにあるグルグルを翻訳する」という考え方です。
これは、うまく言葉にできないことを文章にしていくためのもので、一文一文の内容をより深められるようになります。
この本を読み始めた当初、いわば自分のために文章を書いていたときには、この本の内容をむずかしく感じました。
しかし、人に伝えるという意図をもって文章を書くようになると、だんだんと理解できる項目が増えていったのです。
書くことについてのレベルに応じた学びがある、そんな一冊だと感じます。
こんなひとにおすすめ
- 考えていることを、うまく文章にできないと悩んでいるひと
- 「書くことで伝える」という力をつけたいと思っているひと
2. 書くのがしんどい
この本を読むことにしたのは、ライターになるために学ぶうちにごちゃごちゃとしてきた頭のなかを、整理したいと思ったからです。
「しんどい」なにかがきっとあって、それを客観的に知りたかったのだと思います。
この本のいいところは、文章を書き始めるとぶつかる悩みを、とても具体的に表現しているところです。
そのため、共感できることが多く、とても読み進めやすい内容でした。
また、悩みを解決するために必要な考え方と方法がまとめられているばかりではなく、自分では気づけないようなつまずきを見つけるきっかけも、あちらこちらにちりばめられていたのです。
とくに、「読まれなくてしんどい」という章では、自分の書く文章を客観的に見直すための方法を多く学ぶことができました。
ライターを目指しながら悩むことがあれば、読んでみることで解決の糸口が見つかるかもしれない——そう思える一冊です。
こんなひとにおすすめ
- ライターを目指して記事を書き始めるも、なかなかうまくいかないという悩みごとがあるひと
- 書くことを、しんどいと感じているひと
3. 沈黙のWebライティング
これは、Webライターにとって必須の知識といわれる「SEO」について学ぶために読んだ本です。
631ページにも及ぶ分厚い本ではありますが、イラストを使ったストーリー仕立ての内容なので、読みきることはむずかしくありませんでした。
Webライターが記事を書くために使うツール(キーワードプランナー、アナリティクスなど)の解説から、SEOとはなにか、どのようにして記事の作成に活かすのかという方法まで、丁寧に、そして詳細にまとめられています。
Webで公開する記事を作るときのモラルを学ぶことができたのは、この本を読んでいちばんの収穫でしょう。
なぜなら、信頼されるライターになるために、とても大切なことだと思うからです。
付箋をつけ、何度も読み返しながら、記事を書くために活用しました。
また、記事を書くために下調べをするときの、自分なりの書式作りにも役立ちました。
Webコンテンツを書くためのたいていの基礎知識は、この一冊で学ぶことができるのではないでしょうか。
こんなひとにおすすめ
- SEO知識を身につけたいと思っているひと
- 信頼されるWebコンテンツを作りたいと思っているひと
4. エッセイの書き方
この本は、エッセイの書き方本を探す中で、大変好評だったため読んでみたものです。
ライターといえば、ネット上でよく目にする情報記事のほかにも、さまざまな文章を書く機会があります。
ゆえに、読み手が楽しめるような文章を書く方法を学びたいと思ったことがきっかけでした。
すべて読み終えたとき、この本の内容は、ある大学でのエッセイ講義を書籍に書き下ろしたものだということが分かりました。
そのこともあり、「この通りにしたらエッセイを書くことができそう」という前向きな気持ちになれたことは、読んだ本人のいちばんの驚きです。
「一般人」が、読まれるエッセイを書くためにどう工夫を凝らすのかについて、著者の事例もいれてまとめられています。
それらをかんぺきに習得することはやさしくありませんが、この本の内容を意識して書き続けるうちに、きっと文章力と表現力をあげることは叶うはず——そう思えて、いまでもたびたび読み返している一冊です。
こんなひとにおすすめ
- エッセイをどのように書けばいいのかわからない、というひと
- 読まれるエッセイを書くための方法を知りたいひと
5. 小田嶋隆のコラム道
この本は、読まれるコラムとはどのようにして書かれているのかという工夫、考え方を知るために読んだものです。
いちばん強烈な印象を残した言葉は、つぎのものでした。
「コラムは、道であって、到達点ではない。だから、コラムを制作する者は、方法ではなく、態度を身につけなければならない」
そこから、これはもはや初心者がコラムを書けるようになるための手引書というよりも、コラムに対してどのように向き合っていくのかという「哲学書」なのかもしれないと直感しました。
目次をみると、「コラムとは」からはじまり、「枠組み」「結末」「推敲」、さらにはコラムを書くときの視点についてが並んでいます。
ただ、その内容のまとめ方は、小田嶋隆さん流のコラムとして展開されていて、その世界観に引き込まれていく面白さの要素が強いかもしれません。
コラムを体感しながら学ぶということにおいて、読んでみてよかったと思える一冊です。
「常識を非常識な方法で語る」という著者が、読者の心をつかむ方法を、ご自身の文章を通して教えてくれているのだと解釈しています。
こんなひとにおすすめ
- コラムを書くために、面白いコラムとはなにかを体感してみたいひと
- コラムニストの頭のなかをのぞいてみたいひと
6. 花森安治の編集室
この本を読んだのは、書く仕事の先にある、編集者のことを知りたいと思ったからです。
戦後の日本で異彩を放った伝説の編集長を通して、どのような気持ちで読者と向き合ったらいいのかを学びとることが目的でした。
内容は、著者が、「暮しの手帖」という雑誌の編集長である花森安治さんと過ごした日々をつづったものです。
「花森さんとの出会い」から、「みなさん、どうもありがとう」という最期の別れのときまでの、まるで、伝記物を読んでいるようでした。
ただ、ところどころに、書き手として欠かせない心遣いと、技術的なアドバイスが花森安治さんのセリフのままに書かれているため、心に残る学びがふんだんにあります。
「できるだけやさしく、偉ぶることなく」
この心がけは、とても新鮮で、斬新でした。
読み手を思った記事を書きつづけようという、決意がつよくなる一冊です。
こんなひとにおすすめ
読み手を思うとはどういうことなのか、具体的なエピソードとともに学びたいひと
さいごに
たくさんの文章に触れることで、記事の構成や表現方法など、さまざまな学びがあります。
そして、やはり最後は「書くことをとおして成長しようという意欲」をなくさないことが大切になってくるのかもしれません。
書きつづけている方の書籍を読むことで、そう思うことがあります。
それでは、ライターを目指すなかで気になっていた本を選ぶときの参考にしていただき、いまの自分に必要な知識と少しでもはやく出会うことができますように。